【パンチャカルマリトリート3週間体験記】中心処置
- VYOM Wellness
- 2025年9月16日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年9月18日
3回目の投稿も、すっかり間が空いてしまいましたが、その間に再びケララで過ごしておりました。
8月は日本から14名の方がセンターに1週間滞在され、私は現地でのさまざまなお世話をさせていただきました。
とはいえ、ほとんどの方が私の日本でのヨガの生徒さんや、すでにお会いしたことのある方ばかりでしたので、毎日歓談も楽しみながら過ごすことができました。
さて、6月のパンチャカルマ体験から時間が経ち、記憶も少しずつ薄れてきましたが、ここで改めて思い出しながら、そして自分の中で再び体現しながら綴ってみたいと思います。
いよいよ治療の中心となるプロセスに入り、6日目からは本格的な処置が始まります。
では、その内容を以下にまとめてみます。
〜中心処置となるもの〜
Day6:ヴィレーチャナ(下剤療法)

パンチャカルマの主要な浄化法のひとつで、薬草を使って体内にたまった毒素や余分なピッタ(火のエネルギー)を排出する療法です。 これを飲んだ後、数回に分けて回に分けてトイレに行くことになり、
出でる度に体力は消耗され、その日はほぼ1日をお部屋で過ごしますが、午後にはぐったり…
体に心地よい疲労感があり、午後はゆったり休養します。
この日は特別に朝食抜き・昼食はお粥のみという食事制限があり、胃腸を優しく休ませながら排出の効果を最大限に高めていきます。 私の場合は、このヴィレーチャナとバスティを中心に行いました。
Day7〜:日本とインド国内からの参加者が到着
私のデトックスの山場を越えたタイミングで、日本から、そしてインド国内からも新たな参加者が到着。
それまで一人で静かに過ごしていたリトリートが、いよいよ「みんなで分かち合うリトリート」へと変わっていきました。
正直、パンチャカルマを受けつつコンサルテーションの通訳や滞在中のサポート全般を果たせるのかという懸念もありました。
しかし今回は、前回に比べて治療による身体的な負担が軽く、加えて心の安定も得られていたため、特に乱れることなく過ごすことができました。

施術の時間はもちろんそれぞれに集中するのですが、合間の時間はとても穏やかで心地よい交流のひととき。 グループに分かれて近場のビーチへ散歩に出かけたり、帰国前にはモールへお土産を買いに行ったり。 施術と休養に加え、そんな小さな楽しみも心に残る思い出となりました。
Day7〜13:ナスヤ(鼻の浄化療法)
薬草オイルや煎じ液を鼻に点鼻し、頭部や首、肩まわりの浄化を促します。鼻づまりや副鼻腔の不調、頭痛、肩こり、集中力の低下などにも効果があると言われています。
Day14〜19:バスティ(浣腸療法)
パンチャカルマの「王」とも呼ばれる療法で、薬草オイルや煎じ液を用いた浣腸です。
腸内の浄化を通して、ヴァータ(風のエネルギー)のバランスを整えるのが目的。
腰痛、関節のこわばり、神経系の不調にまで効果があるとされ、古典の中でも非常に重要視されている処置です。
ヴァータは「動き」を司り、呼吸・血液の循環・神経伝達・排泄など、体のあらゆる働きをコントロールしており、そのヴァータの本拠地は「大腸」。
つまり、大腸を直接ケアできるバスティは、全身の調整に直結するのです。
施術は数日間にわたり、大小のバスティを交互に行う形で進みました。 オイルの量が多い日と少ない日を繰り返しながら、解毒と滋養を同時に行い、腸の中をやさしく洗い流し、必要な潤いを与えていきます。
〜様々なトリートメント〜
Day6〜20:
中心処置の合間にも、アビヤンガ(全身オイルマッサージ)はじめ、シーロダーラ、その他さまざまな薬草やオイルを使ったトリートメント受けました。
油剤療法
マルママッサージ=マルマ(エネルギーポイント)を刺激するもの
シンクロナイズド・アビヤンガ=2人のセラピストが同時に行う
チューヴァティ・ウッザーチル=足で踏むように行うケララ式
ナスヤ(鼻の治療)
ネトラタルパナ(目のオイル治療)
カルナ・ドゥーマパーナ(耳に薬草の煙を入れる施術)
発汗療法
エラキリ(薬草の葉を炒めたポットでマッサージ)
ポディキリ(乾燥薬草の粉末を布で包んで押し当てる)
ナヴァラキリ(ケララ特有の薬用米をミルクで煮て温湿布のように用いる)


リトリートの期間中、とにかく全身オイル漬けの日々。
外からもオイル、中からもオイル…。
アビヤンガ(全身オイルマッサージ)、ナスヤ(鼻の浄化)、バスティ(浣腸療法)など、ほぼ毎日どこかしらにオイルが入っていきます。
「ここまでやる必要があるの?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、アーユルヴェーダの古典書をひもとくと、その理由が見えてきます。
なぜオイルなのか ― 古典書の視点
アーユルヴェーダの古典『チャラカ・サンヒター』や『スシュルタ・サンヒター』には、スネハナ(オイル塗布・油剤服用)が繰り返し強調されています。
ポイントは大きく3つあります。
乾きを潤す
人の体は加齢やストレス、過労などで「乾燥(ヴァータの乱れ)」が進みます。 オイルはその乾きを補い、組織を柔らかく保つ働きがあります。
浸透し、毒素をゆるめる
オイルは皮膚や組織に浸透し、体内にこびりついたアーマ(未消化物・毒素)をゆるめ、移動しやすくしてくれます。 これが後のパンチャカルマにおける排出法(ヴィレーチャナやバスティ)につながります。
滋養と安定を与える
油は「オージャス(生命エネルギー)」を養い、心身に安定感と落ち着きをもたらすとされます。
中心処置(パンチャカルマ)期間:食事について
7日目から、ようやく常食に。
中でも空腹で味わう朝食は毎日の楽しみの一つ。

こちらはほぼ毎日いただいてた、”ギードーサ”と”スチームドバナナ”はお気に入りの定番メニューです。
パンチャカルマの期間中は、食事そのものが治療の一部として扱われます。 オイルや浄化療法で体内に働きかけているため、同時に消化器官への負担を最小限に抑えることが大切だからです。
しかし、アーユルヴェーダ治療中とはいえ、3回の食事は楽しみたい!
厳格な食事制限で楽しみを失いたくない! そんな願いが、ここでは自然に叶います。 シンプルながらも体が求める味わいがあり、食べるたびに満たされる感覚が味わえます。
ヴィレーチャナ(下剤療法)の日
朝食はなし、昼食はシンプルなお粥のみ。
消化をやさしく保ちながら、体内の毒素をしっかり排出させることに集中します。
それ以外の日
「常食」です。 とは言っても、センターで出される食事はとても消化に優しく整えられています。
消化しやすい軽い性質の豆類や野菜の煮込み
油やスパイスは控えめで軽やか
温かく、胃腸に負担をかけない味つけ

シンプルながらも体が欲しているものを満たしてくれる食事で、食後の重だるさや罪悪感がなく、内臓がどんどん軽くなっていく実感がとても心地良い。
常食に変わる日から、薬草の服用も始まります。
最後に..... 体験を通じて感じたこと
オイル漬けの日々を過ごす中で、肌の質感や体の軽さが変わるだけでなく、心も穏やかになり、眠りも深くなっていきました。 古典書が伝える「オイルは心身を柔らかくする」という言葉を実感できます。
そして何よりも毎回感動するのは、明らかに思考がクリアになり、心が安定するというメンタル面でのデトックス効果です。 からだの調子が整うだけでなく、健康そのものが日を追うごとに積み重なっていくような感覚。
私はここ数年、年に一度のペースでパンチャカルマを受けています。
そのたびに感じるのは、どんどん「健幸度」が増していくこと。
例えば、具体的な変化というと…
・慢性的な疲労感が軽くなる
・気になっていた抜け毛がなくなった
・ホルモンバランスが整い生理前の辛さがなくなった
・消化力が高まり、食後の重だるさや眠気がなくなる ・ここ数年、大きな病気もなければ、薬(西洋医学の)を飲むほどの病気さえ罹ってない
といった身体面での変化に加えて、
・人に対して優しく、穏やかに過ごせる
・これまでなら気にしていたことも、受け入れられる心でいられる
・記憶力が増した(ように感じる)
など、精神面での変化は、思いがけないけれど本当にありがたい副産物です。
こうした変化が少しずつ積み重なり、毎年「前回より健幸度が上がっている」と実感できるのです。
パンチャカルマは単なるデトックスではなく、体質に合わせてオイルや処置が行われるため、続けるほどに深いレベルで心身が整っていきます。
まさに「年ごとに新しい自分に生まれ変わる」ような体験です。
パンチャカルマは、体調不良や不調がある人だけのためのものではありません。 健康な人こそ、より健やかに、より自分らしく生きるために体験していただきたい。 改めてそんな強い想いを持ちました。 そして、アーユルヴェーダの良さを少しでも多くの人に伝えたい
そのためにも自分自身が健幸でいることに努めようと思います。

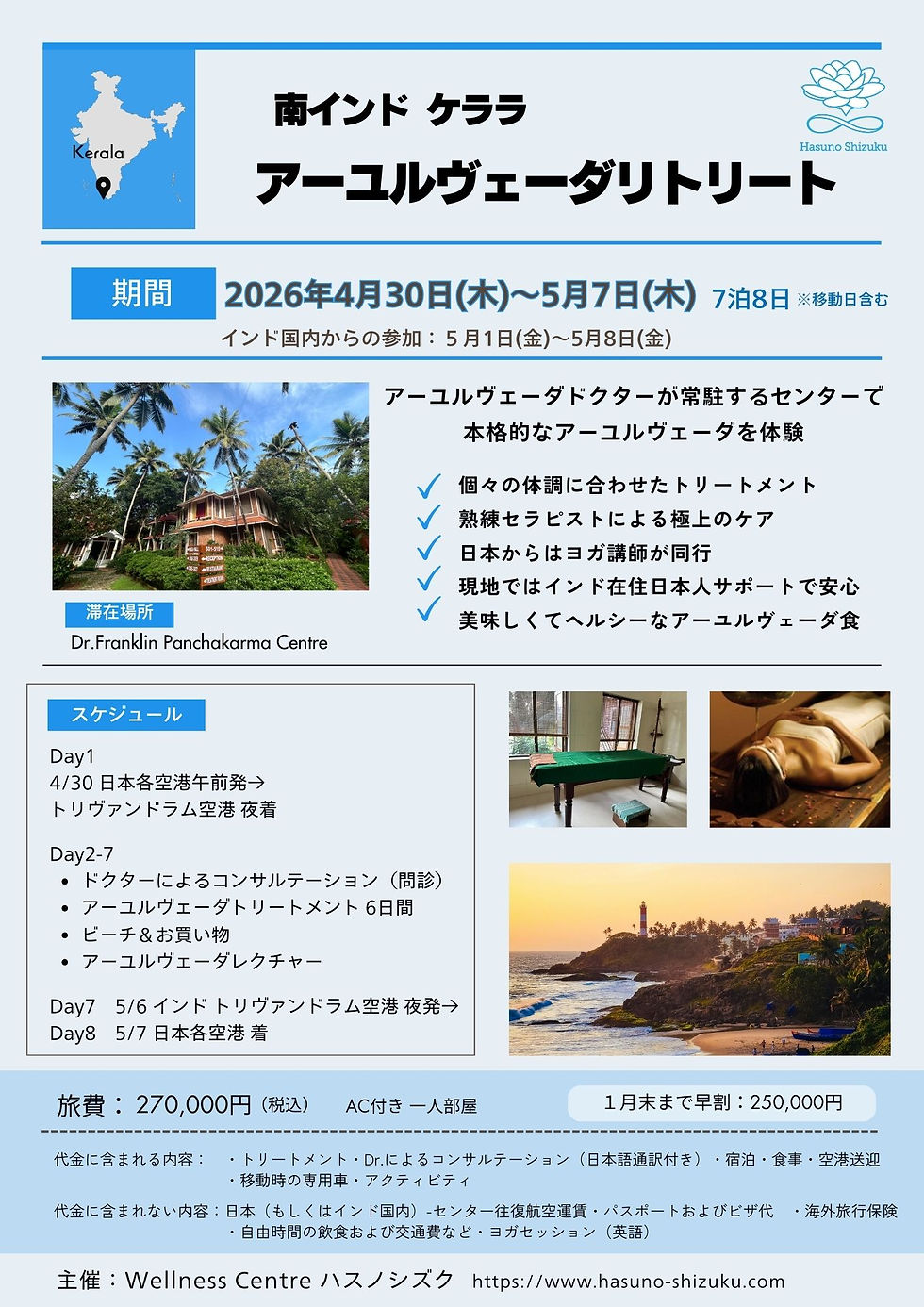


コメント